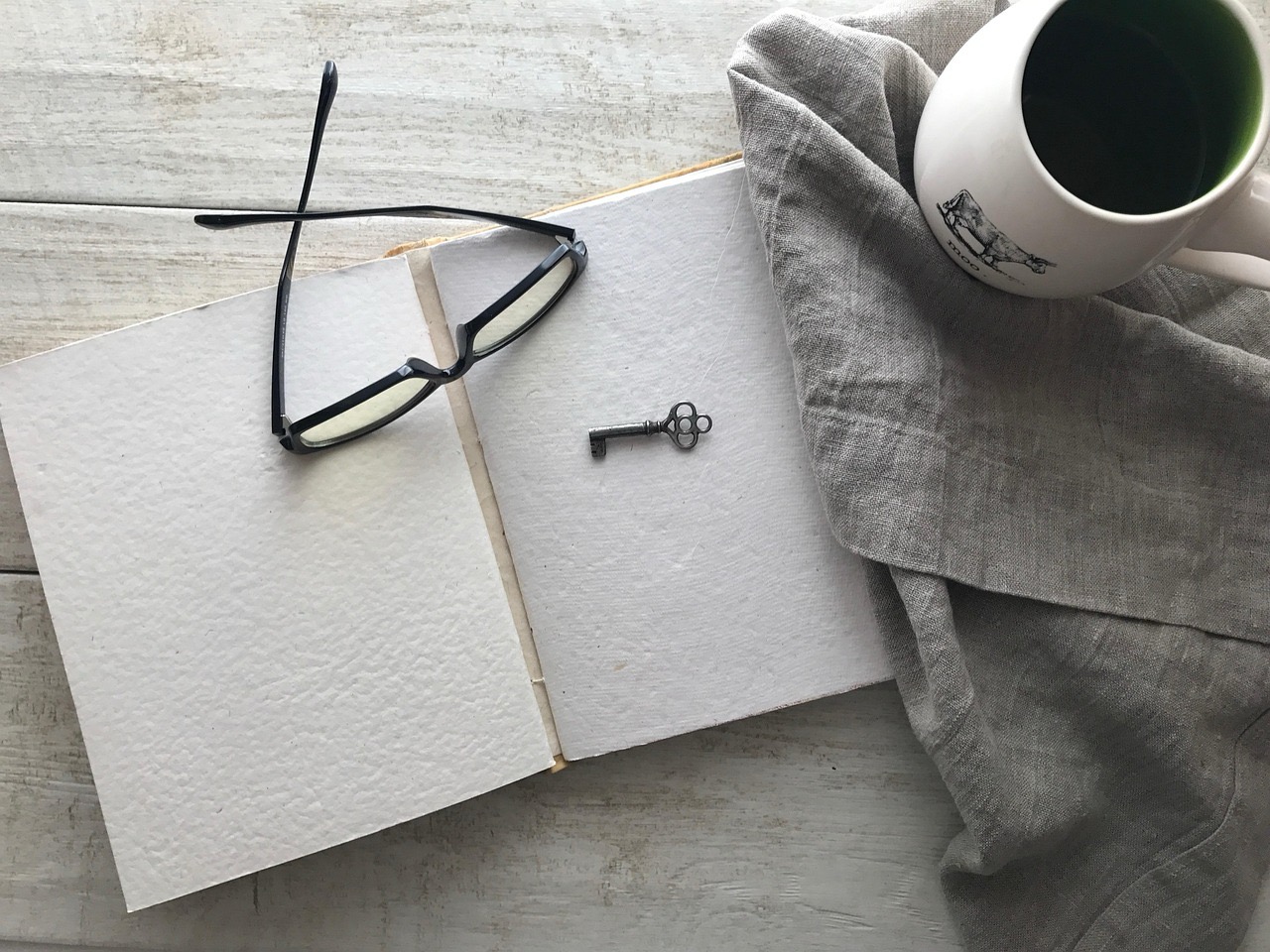目次
包括申請とは?ドローン飛行のための特別な許可制度
ドローンを業務などで頻繁に飛行させる場合、都度の「個別申請」は大きな手間と時間の負担になります。そんなときに活用できるのが「包括申請」です。包括申請とは、国土交通省が認可する一定条件下での反復的な飛行を、一括してまとめて申請・許可が得られる制度です。
この制度を活用することで、全国各地での飛行や、夜間・目視外といった特殊な飛行にも柔軟に対応でき、効率的かつ安定的な運用が可能になります。特に業務利用者にとっては、作業効率の向上と法的リスクの軽減の両面で大きなメリットがあるため、多くの事業者が導入しています。
- やり方:
包括申請のやり方はオンライン申請システム「DIPS」を通じて行います。申請のやり方がわからない場合は、国交省のガイドラインや記入例を参考にすることでスムーズに進められます。 - 不要:
趣味で数回飛行するだけのユーザーは包括申請は不要です。包括申請はあくまで反復的・業務的飛行を対象としています。 - できること:
包括申請を取得すれば、DID(人口密集地)での飛行や夜間・目視外飛行など、通常の申請では難しい飛行も可能になります。これにより、より多様なドローン業務ができるようになります。
個別申請との違いと包括申請の定義
「個別申請」は飛行のたびにその都度、日付・場所・飛行内容などを細かく記載して許可を取る必要があります。これに対し、「包括申請」は、一定の飛行条件や業務内容に該当すれば、1年間有効な許可を一括で取得できる制度です。
たとえば、空撮会社が全国各地で同様の飛行業務を年間通じて繰り返す場合、個別申請を毎回行うのは非常に非効率です。包括申請であれば、その業務の反復性が認められれば、複数地域・複数日時にわたって包括的に許可されるため、現場のスケジューリングが飛躍的に楽になります。
包括申請のメリットとは?時間・手間を省ける理由
包括申請を行う最大の利点は、業務効率の大幅な向上です。以下のような具体的なメリットがあります。
- 申請の手間が減る:都度の飛行計画を提出せずに済むため、事務作業が簡略化されます。
- 柔軟な運用が可能:急な飛行が必要になった際にも、許可済みの範囲内であれば即時対応ができます。
- 年間を通じた計画が立てやすい:飛行日や場所を事前に確定していなくても、包括的な許可があれば業務計画の自由度が増します。
- 行政審査の回数削減:審査コストや担当者のやり取りが最小限に抑えられ、行政対応に要する時間が削減されます。
これらの理由から、業務で頻繁に飛行する法人・個人にとっては事実上必須ともいえる制度です。
包括申請が必要なケースと対象者の特徴
包括申請は、反復・継続的にドローンを飛行させる予定がある操縦者や事業者に適した制度です。単発的な飛行や趣味利用とは異なり、業務の一環として何度も飛行するようなケースでは、個別に申請するよりも包括申請の方が圧倒的に効率的です。
ここでは、どのようなケースが「包括申請の対象」となりうるのか、また対象者の具体的な特徴について詳しく解説します。
10時間:二等無人航空機操縦士の資格取得には最低10時間の飛行訓練が必要とされており、資格保持者は審査でも有利に働きます。
カテゴリー:包括申請が必要なカテゴリーには、空撮、測量、設備点検、農業支援、災害調査などがあります。
反復・継続的な飛行業務とはどういうことか
包括申請が認められるには、「反復・継続的な飛行」が前提となります。これは単なる「複数回の飛行」ではなく、業務として一定の頻度で同様の飛行を繰り返すことが条件です。
たとえば、以下のような業務が該当します:
- 建設現場の進捗管理を毎週ドローンで撮影する
- 太陽光パネルの点検を各地で定期的に実施する
- 自治体の依頼により定期的なインフラ点検を行う
- 映像制作会社が継続してCMや番組撮影を担当する
国土交通省では、概ね月に1回以上、年間で複数回の飛行が予定されている場合は包括申請の対象とみなす傾向があります。ただし、単に飛行回数が多ければよいわけではなく、飛行の内容・目的・場所などが共通していることがポイントです。
空撮・点検・測量など、主な適用業務の事例
包括申請が活用される業種・業務は非常に多岐にわたります。特に以下のような事業では、実務上の必要性から高確率で包括申請を行っています:
- 空撮業務:CM・映画・イベント・不動産などの撮影業務。
- 点検業務:橋梁、送電線、ソーラーパネル、ビル屋上などの点検。
- 測量業務:土地開発・造成工事・公共事業における3D測量や現況調査。
- 農業関連:農薬散布や生育状況の定期的な観測。
- 災害対応・報道:災害時の被災状況確認や報道関係の空撮。
こうした業務では、飛行条件が類似する案件を複数抱えることが常態化しているため、包括申請を行うことで法令遵守と業務効率を両立させることができます。
包括申請で許可される飛行の範囲と条件
包括申請によって許可される飛行には、一定の範囲と条件が設定されています。すべての飛行に自由に適用できるわけではなく、航空法に基づく規制対象のうち、包括的に許可できる飛行項目に限られる点に注意が必要です。
許可される範囲は、飛行場所・時間・方法などに明確な基準があり、飛行のリスクが比較的低いと判断される条件であることが原則です。以下でその具体的な内容を見ていきましょう。
飛ばせる場所:
包括申請では、条件付きで日本全国の人口密集地や特定飛行空域内でも飛ばせる場所として許可されます。
特定飛行:
包括申請で許可されるのは、航空法で定められた「特定飛行」のうち、比較的リスクの低い6項目です。
補助者なし:
補助者なしでの目視外飛行は原則不可ですが、適切な安全対策と飛行マニュアルの記載があれば審査で通る可能性があります。
レベル3 / レベル3.5:
2024年以降、物流分野などで注目されているレベル3およびレベル3.5の飛行を行う場合、包括申請とは別に特定運航申請が必要です。
プロペラ・ガード:
人口密集地や接近飛行を行う場合には、プロペラガードの装着が必須とされることが多く、マニュアルへの記載が推奨されます。
飛行できるエリアや地理的な制限
包括申請では、基本的に「全国包括」と呼ばれる広範なエリアでの飛行許可が取得できます。ただし、実際に飛行するには以下のような地理的制限を受けます:
- DID(人口集中地区)での飛行:許可対象。ただし、地元自治体や土地所有者の承諾は必要。
- 空港周辺・一等空域・イベント会場上空:包括申請では対象外。個別許可が必要。
- 国立公園・都市公園・文化財エリアなど:飛行そのものが制限されている場合があるため、別途申請や承認が必要。
つまり、全国的に飛行できるとはいえ、飛行前の現地調査と関係者への事前連絡は欠かせないというのが実情です。
夜間飛行・目視外飛行・イベント上空などの許可項目
包括申請で取得できる主な飛行項目は、航空法の「飛行の方法」制限に該当する以下の6項目です:
- 人口集中地区(DID)での飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行(FPV含む)
- 30m未満の接近飛行(人・建物など)
- イベント上空での飛行
- 危険物の輸送・物件の投下(通常は対象外)
これらのうち、「危険物輸送・物件投下」を除いた5項目は、包括申請で認められることが一般的です。ただし、飛行マニュアルで安全対策が十分に明記されていることが前提となります。
特に、目視外・夜間飛行はリスクが高いため、国交省は操縦者の技能証明(資格)や過去の飛行実績を重視する傾向にあります。
航空法で求められる申請区分と対応内容
包括申請の対象となるのは、航空法第132条の「飛行の空域」と132の2の「飛行の方法」に該当する飛行です。それぞれ以下のように区分されます:
■ 飛行の空域に関する許可(第132条)
- 人口集中地区(DID)
- 空港周辺(包括不可)
- 高高度(150m以上、基本的に包括不可)
■ 飛行の方法に関する承認(第132条の2)
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 接近飛行(30m未満)
- イベント上空での飛行
- 危険物輸送・物件投下
包括申請では、比較的リスクが管理しやすい項目に限定して許可・承認を取得できるようになっています。逆に、空港周辺や高高度の飛行は対象外となるため、別途個別申請が必要です。
ドローン包括申請の手続き方法と必要書類
包括申請は、国土交通省が運営するオンラインシステム「DIPS(ドローン情報基盤システム)」を通じて申請します。紙媒体では受け付けておらず、全てオンライン上で完結する仕組みです。
初めての申請では、操作に戸惑うこともありますが、ポイントを押さえておけばスムーズかつ確実に申請を完了させることが可能です。このセクションでは、申請手順と必要書類、そしてよくあるミスを防ぐためのチェックポイントを解説します。
記入例:
DIPS入力画面では、国交省が記載した記入例を参考にしながら申請書を作成することができます。
機体登録:
使用する機体は、リモートIDに対応した機体登録済みのドローンである必要があります。登録されていない場合、許可は下りません。
操縦者追加・機体追加:
申請後に操縦者や機体を追加したい場合は、DIPSから「変更申請」を行うことで対応可能です。
申請先:
包括申請の申請先は国土交通省の航空局であり、DIPSを通じてオンラインで行います。
DIPSでのオンライン申請の流れ
DIPSによる包括申請は、以下のステップで進められます:
- アカウント作成とログイン
国交省のDIPSポータル(https://www.dips.mlit.go.jp/)にてアカウントを作成します。 - 飛行計画の登録
包括申請でも、予定飛行の範囲や対象エリアを指定する必要があります。 - 申請書の入力
飛行目的、使用機体、操縦者情報、飛行方法などを詳細に記載。 - 添付ファイルのアップロード
飛行マニュアル・機体情報・操縦者実績などを添付。 - 申請送信と審査待ち
送信後、審査に数日〜数週間程度かかることがあります。
申請が承認されると、DIPS上に許可番号や条件が表示され、飛行前には別途「飛行計画の提出」も必要となる点に注意しましょう。
添付書類や飛行マニュアルの作成ポイント
包括申請では、次のような添付書類の提出が求められます:
- 飛行マニュアル(国交省フォーマット or 独自マニュアル)
- 操縦者の実績・資格証明(免許・修了証)
- 使用機体の仕様書・写真
- 安全対策資料(緊急時対応フローなど)
飛行マニュアルは、国交省が公開している「標準マニュアル(業務用)」をベースにするか、独自マニュアルを作成します。独自マニュアルを提出する場合は、夜間飛行や目視外飛行など、申請項目に応じたリスク管理方法を明記する必要があります。
なお、機体は登録済みであること(リモートID対応含む)が前提です。
申請ミスを防ぐためのチェックリスト
DIPSでの包括申請では、記載ミスや添付漏れによって申請が却下されたり、審査が長引いたりすることがあります。以下のポイントを事前に確認しましょう:
- □ 使用機体が国交省の基準を満たしているか
- □ 操縦者の資格・実績が要件を満たしているか
- □ 飛行マニュアルに不足項目がないか(例:通信断時の対応など)
- □ 対象となる飛行エリアが包括申請の範囲内か
- □ すべての必要書類が正しい形式で添付されているか
特にマニュアルの内容と申請項目が矛盾していると高確率で差し戻されるため、申請前のチェックは念入りに行いましょう。
包括申請にかかる費用と審査にかかる日数
ドローンの包括申請を行う際には、申請にかかる費用や審査期間の目安を事前に把握しておくことが重要です。
また、自力で申請する場合と行政書士などの専門家に依頼する場合では、必要となるコストや手間が大きく異なります。
このセクションでは、申請にかかるコストと時間、そして申請手法ごとの違いについて詳しく解説します。
審査期間の目安と申請タイミング
包括申請の審査期間は、通常2週間〜1ヶ月前後が目安です。ただし、以下のような要因によって前後することがあります。
- 国交省の繁忙期(年度末や夏季など)
- 提出書類に不備がある場合
- 独自マニュアルを提出する場合(審査が長引く傾向あり)
特に業務での使用を予定している場合は、最低でも1ヶ月前には申請を開始するのが理想的です。直前になって申請しても、審査が間に合わず飛行ができなくなるリスクがあります。
また、更新申請の場合も、有効期限が切れる1ヶ月前を目安に準備を始めましょう。
行政書士に依頼した場合の費用相場
包括申請を行政書士などの専門業者に依頼する場合の費用は、おおむね3万円〜10万円程度が相場です。価格は次の要素で変動します:
- 申請内容の複雑さ(飛行項目数、独自マニュアルの有無)
- 業者の対応範囲(DIPS入力のみ or 書類作成から全代行まで)
- 納期の希望(特急対応の有無)
安価な業者ではテンプレートベースの申請代行が中心ですが、専門性の高い行政書士であれば、事業の実態に合わせてマニュアル作成まで対応してくれるケースもあります。
また、許可取得後の「更新サポート」や「飛行計画提出の代行」までセットになっているパック商品も存在します。
自力申請と代行依頼のコスト比較
自力申請であれば、費用は基本的に無料(行政手数料なし)で行うことができます。ただし、以下のようなデメリットが伴います:
自力申請の特徴:
- メリット:費用を抑えられる(0円〜)
- デメリット:申請ミス・不備による差し戻しのリスクが高い/学習・作成時間の負担
代行依頼の特徴:
- メリット:短期間で確実に申請できる/業務に専念できる
- デメリット:コストがかかる(3〜10万円前後)
「時間をかけてでも自分で勉強したい」「定期的に申請するからノウハウを蓄積したい」という方には自力申請もおすすめです。一方、業務を止めたくない・確実に通したい場合はプロに任せるのが得策です。
包括申請が通りやすくなる実務上のポイント
包括申請は、単にフォームを埋めて送信すれば許可が下りるというものではありません。国土交通省の審査担当者が、安全性・信頼性・運用能力を評価した上で許可を出すため、申請内容には実務に基づいた信頼性が求められます。
このセクションでは、申請の通過率を高めるために意識すべき具体的なポイントを解説します。
操縦者の資格や飛行実績の提出の重要性
審査の際に重視される要素のひとつが、「操縦者の能力と経験」です。具体的には、次のような情報の提出が推奨されます:
- 二等無人航空機操縦士(国家資格)の写し
- 民間資格(JUIDA、DPAなど)の修了証明書
- 飛行ログ(年間飛行回数・飛行時間・飛行目的など)
飛行実績が十分にあると判断されれば、夜間飛行や目視外飛行などの高リスク飛行についても包括許可を得やすくなる傾向があります。
また、法人の場合は「誰が飛行するのか」を明記し、複数操縦者がいる場合には全員分の資格・経験を記載するのが望ましいです。
リスク対策マニュアルに含めるべき内容
包括申請の審査では、「安全管理体制」や「緊急時対応能力」も重要な判断材料です。その中核となるのが「飛行マニュアル」です。特に独自マニュアルを提出する場合、以下のような項目は必ず含める必要があります:
- 通信が途絶した場合の対応(RTH設定、手動復帰手順など)
- 夜間飛行時の視認対策(機体への灯火、地上支援体制など)
- 目視外飛行時の補助者配置と連携方法
- 人や物件との距離確保の方法
- 飛行前・飛行後のチェックリストと点検項目
- 緊急時の連絡体制・119/110通報の基準
マニュアルは単なる形式文書ではなく、操縦者が実際に遵守できる現実的かつ具体的な内容であることが重要です。国交省の「標準マニュアル」を流用する場合でも、自社の運用実態に合った補足説明を加えることが、通過率アップのカギとなります。
包括申請の有効期間と更新・再申請の流れ
包括申請は一度許可を得れば、一定期間のあいだは個別申請なしに飛行が可能となる便利な制度ですが、永久に有効ではなく、原則として1年間の有効期限があります。そのため、期限管理と適切な更新手続きが非常に重要です。
ここでは、包括申請の有効期間や、更新・再申請のタイミングと手続きの流れを詳しく解説します。
有効期限のルールと更新時の注意点
包括申請の許可の有効期間は原則1年間とされています。許可証には「有効期間開始日」と「有効期間満了日」が明記されており、満了日を過ぎるとその許可は無効となります。
更新申請を行う際のポイントは以下のとおりです:
- 原則として、満了日の1ヶ月前までに再申請を行うのが理想
- 更新時も初回申請と同様に審査が必要(自動更新ではない)
- 実績を踏まえた改善点・変更点がある場合は、マニュアルや運用体制に反映させること
- 飛行実績のログ提出を求められる場合もある
また、機体や操縦者、飛行条件に大きな変更がある場合は「更新」ではなく「新規申請」として扱われることがあるため、変更点がある場合は事前に確認しておくと安心です。
更新忘れによるリスクとスケジュール管理
包括申請の更新を忘れた場合、有効期限以降の飛行は無許可飛行として法令違反となる可能性が高くなります。
たとえ業務が継続中でも、「一時的に飛行ができない」状況が発生するリスクがあるため、次のような対策が重要です。
- 社内で許可期限をカレンダーや管理表に登録し、期限前に通知する体制を構築
- 定期的にDIPSのマイページを確認し、許可一覧をチェック
- 年度ごとに実績ログを整理・保存しておき、更新申請に備える
また、申請混雑時期(例:年度末・夏季)には審査が遅延するケースもあるため、余裕をもったスケジュール管理が、無駄な業務停止を防ぐ鍵になります。
ドローン包括申請で起きやすいトラブルとその対処法
包括申請は業務効率を大きく改善する便利な制度ですが、申請過程や運用中にトラブルが発生するケースも少なくありません。多くは書類の不備や運用上のルール違反が原因であり、事前に注意しておくことで回避できます。
ここでは、実際に多くの操縦者・事業者が経験した典型的なトラブルと、その対処・予防方法について解説します。
申請書類の不備による却下事例
DIPSによる包括申請で最も多いのが「書類不備による差し戻しや却下」です。よくある例としては以下の通りです:
- 飛行マニュアルに記載漏れがある(例:通信断時の対応策がない)
- 操縦者情報が最新でない(退職者や未資格者が記載されたまま)
- 使用機体の情報が未登録または型式不明
- 飛行目的や方法が申請項目と一致しない
これらの不備があると、申請が自動的に却下または差し戻しとなり、再提出を求められることになります。
対策としては、申請前に次のような対処を行うことが重要です:
- 国交省の申請ガイドラインを熟読する
- 標準マニュアルをベースに自社運用に合った内容を加筆する
- 他者による**事前レビュー(ダブルチェック)**を実施する
許可条件に違反した場合の対応と指導例
包括申請で許可を得たからといって、どんな飛行でも自由に行えるわけではありません。許可証には必ず「許可条件」が明記されており、それに違反した場合は以下のような事態に発展することがあります:
- 国交省からの是正指導
- 許可の一時停止または取り消し
- 最悪の場合、航空法違反での処分や書類送検
違反事例には以下のようなケースがあります:
- 許可された飛行区域外で飛行した
- 補助者を配置せずに目視外飛行を実施
- 許可されていない飛行方法(例:物件投下)を行った
- 飛行計画を提出せずに飛行を実施
これらを防ぐためには、飛行前に許可条件を再確認する習慣を持つこと、そしてスタッフ全員に条件遵守の意識を徹底させることが求められます。
また、万一トラブルが発生した場合は速やかに国交省へ報告し、誠実に対応する姿勢が今後の信頼確保につながります。
行政書士への依頼は必要?自分で申請するかの判断基準
ドローンの包括申請は、DIPSを使えば誰でも自力で申請可能です。しかし、実際には多くの事業者が行政書士などの専門家に依頼しているのも事実です。
ここでは、「自分でやるべきか、それとも専門家に任せるべきか」を判断するための基準や、各選択肢のメリット・デメリットを整理して解説します。
自力で申請できる人の特徴と注意点
以下のような方は、自力での申請に比較的向いています:
- DIPSの基本操作に慣れている
- 標準マニュアルで対応可能な業務内容(シンプルな空撮など)
- 過去に包括申請の経験がある、または学習意欲が高い
- 社内に申請業務の専任者がいる
自力申請の大きなメリットは費用がほぼゼロで済むことです。しかし、以下のような注意点も存在します:
- 記載ミスや添付漏れのリスク
- 書類作成・準備に時間がかかる(初回は数日〜1週間程度)
- 審査での差し戻しによるタイムロス
初めての申請であっても、手間と時間を惜しまなければ十分に自力で対応可能です。ただし「急ぎの業務」「複雑な申請内容」がある場合は要注意です。
行政書士に頼むメリット・デメリット
行政書士などの代行業者に依頼する最大の利点は、「申請の通過率が高く、スムーズに許可が得られる」ことです。
メリット:
- プロが書類を整えるため、審査落ちのリスクが低い
- 独自マニュアルの作成支援や飛行実績の整理も対応可能
- DIPS操作の代行や問い合わせ対応も任せられる
- 忙しい現場担当者の業務負担を大幅に軽減できる
デメリット:
- 費用がかかる(3〜10万円程度)
- 内容によっては修正やヒアリングが必要なこともある
- 一部の業者はテンプレート対応のみで柔軟性に欠ける場合もある
業務として確実性が求められる場合や、リスクの高い飛行内容を含む申請には、専門家のサポートが非常に効果的です。
どんなケースで専門家に依頼すべきか
以下のようなケースでは、行政書士などの専門家に依頼するのが安全かつ効率的です:
- 初めての包括申請で不安がある
- 夜間・目視外など複数の飛行項目を含む
- 独自マニュアルの作成が必要
- 社内に申請経験者がいない
- 業務が多忙で申請作業に時間を割けない
- 許可取得を急いでいる(特急対応を希望)
特に、業務用に包括申請を活用する法人・自治体などは、将来の更新や記録整備まで視野に入れて外部に依頼するのが賢明な選択となることも多いです。
よくある質問(FAQ)
ドローンの包括申請は将来的になくなるのでしょうか?
2025年現在、包括申請は引き続き制度として継続されています。国土交通省は運用改善を進めつつも、包括申請の利便性を評価しており、制度そのものが廃止される見通しは今のところありません。ただし、国家資格制度の普及により、運用ルールや申請方法が変わる可能性はあるため、最新の情報を随時確認することが大切です。
包括申請をするための具体的な条件は何ですか?
主な条件は以下のとおりです:
- 業務として反復的・継続的に飛行を行う予定があること
- 飛行内容・飛行場所・飛行方法が一定の基準に適合していること
- 操縦者に十分な経験や資格があること
- 飛行マニュアルと安全対策が適切に整備されていること
これらの条件を満たすことで、全国を対象とした飛行や、夜間・目視外飛行などの承認が受けやすくなります。
包括申請にかかる費用はいくらくらいですか?
自力申請の場合、国への手数料は無料です。ただし、準備や学習の時間的コストは発生します。行政書士などの代行業者に依頼する場合は、おおむね3万〜10万円前後が相場です。申請内容の複雑さや納期、サポート範囲により料金は変動します。
包括申請と個別申請はどちらが向いていますか?
飛行回数が少なく、1回限りのイベントや単発の撮影の場合は個別申請のほうが適しています。一方、月に複数回の業務飛行や、全国での移動飛行を行う場合は包括申請の方が圧倒的に効率的です。運用形態に応じて使い分けましょう。
包括申請の許可が下りるまでの期間はどのくらいですか?
通常、申請から2週間〜1ヶ月程度で審査結果が出ます。ただし、年末や年度末などの繁忙期、または申請内容に不備がある場合はさらに時間がかかることがあります。特に独自マニュアルを使用する場合は、審査が長引く傾向があります。
包括申請を一度取得すればすべての飛行に対応できますか?
いいえ、すべての飛行に対応できるわけではありません。例えば、空港周辺での飛行や150m以上の高高度飛行、危険物の輸送などは、包括申請ではカバーできないため、個別に申請が必要です。包括申請でカバーされる範囲はあくまで「比較的リスクの低い反復飛行」に限定されます。
包括申請はいつまで有効ですか?
原則として1年間有効で、継続利用には更新手続きが必要です。
レンタルドローンでも包括申請は可能ですか?
はい。ただし、機体が機体登録されていること、マニュアルに機体情報を正しく記載することが条件です。
YouTubeで空撮を配信するには包括申請が必要ですか?
商用利用と判断される場合は、DID上空や夜間飛行などの特定飛行に該当し、包括申請が必要になるケースがあります。
包括申請に必要なものは?
縦者情報・飛行マニュアル・登録済み機体情報・飛行経歴・マップ情報・補助者体制などが必要です。