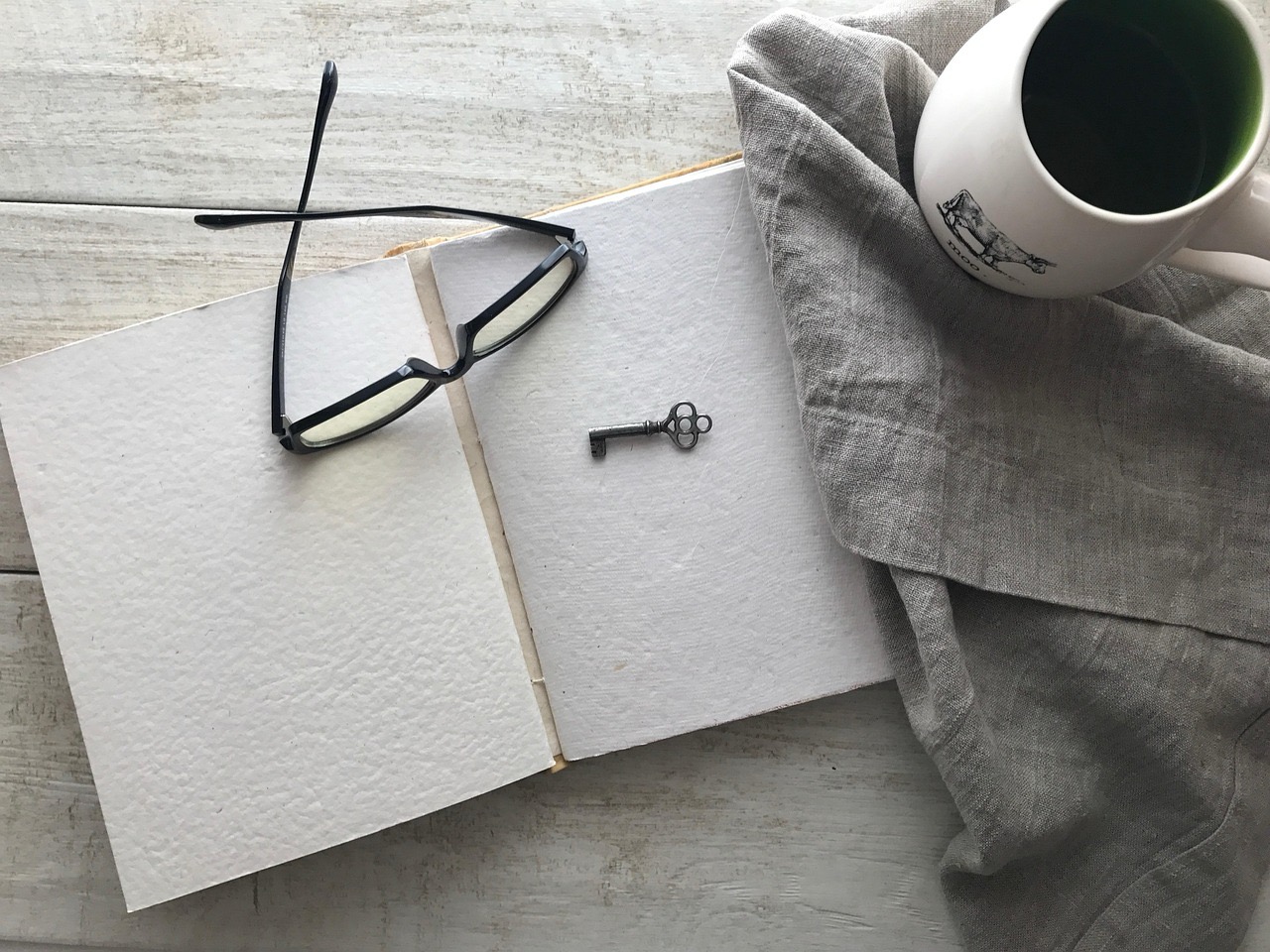目次
ドローンの国家資格とは?まずは基礎知識を押さえよう
日本において「ドローンの国家資格」とは、国土交通省が定める「無人航空機操縦士」のことを指します。2022年12月より制度が開始され、これまで民間資格のみで運用されていた操縦スキルの評価に、公的な基準が設けられるようになりました。
国家資格は、特定の条件下(例えば「目視外飛行」や「有人地帯での補助者なし飛行」など)の飛行を実現するために必要であり、業務としてドローンを活用する上で今後ますます重要な位置づけとなります。
民間資格と国家資格の違い
民間資格は、JUIDAやDPAといった団体が独自に定めていた講習・試験によって発行されるもので、飛行に関する法的効力はありませんでした。民間資格を持っていても、航空法で定める飛行許可・承認が必要なケースでは、別途国土交通省への申請が必須です。
一方、国家資格である「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」は、国が認定する登録講習機関での講習や試験を経て取得する公的な資格であり、特定の飛行においては許可・承認の一部が免除される利点があります。また、警備、測量、点検などの産業用途でも、国家資格保持者を求める企業が増えています。
国家資格が必要な場面とは
国家資格が必要となるのは、主に以下のような高リスクの飛行を行う場面です:
- 補助者なしでの目視外飛行(レベル4飛行)
- 人口密集地上空での飛行
- 夜間飛行や物件投下など、危険性が高い飛行形態
- 公共インフラや重要施設での業務飛行(点検・測量・警備など)
これらの飛行を行うには、国家資格を取得し、所定の申請・登録を行うことで一部の承認手続きが簡略化され、効率的な運用が可能となります。特に一等操縦士は、有人地帯での補助者なし目視外飛行が許可される唯一の資格であり、物流や社会インフラ分野での活用が期待されています。
ドローン国家資格の種類|一等・二等の違いと選び方
ドローンの国家資格には「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の2種類があり、それぞれが対応する飛行形態や用途に違いがあります。目的に応じて取得すべき資格が異なるため、自身の運用ニーズを明確にしたうえで選択することが重要です。
一等無人航空機操縦士とは
一等操縦士は、最も高いレベルの国家資格であり、「補助者なしの目視外飛行(いわゆるレベル4飛行)」が可能となります。この飛行は、たとえば住宅街などの有人地帯上空で、補助者を配置せずにドローンを操縦するもので、極めて高度な安全管理が求められます。
一等資格を取得することで、物流や災害対応、警備といった高度な業務用途において、飛行申請の一部が免除されるため、即戦力としての価値が高まります。
ただし、試験内容は二等に比べて格段に難易度が高く、講習・審査も厳格なものとなっているため、ある程度の経験と準備が求められます。
二等無人航空機操縦士とは
二等操縦士は、補助者ありでの目視外飛行や、夜間飛行、危険物の輸送、物件投下などに対応するための国家資格です。たとえばインフラ点検、農薬散布、測量、空撮といった産業利用において、より多くの業務飛行に柔軟に対応できるようになります。
二等資格は一等に比べて取得ハードルがやや低く、講習を受けたうえで修了審査をパスすれば、比較的短期間・低コストでの取得が可能です。これから業務でドローンを活用していきたいという初心者にもおすすめの資格といえます。
一等・二等のどちらを取るべきか
どちらの資格を取るべきかは、あなたのドローンの利用目的に左右されます。
- 物流や災害対応、都市部での高度な業務飛行を予定しているなら、一等操縦士が必須
- インフラ点検、農業、測量、空撮、民間の業務利用を想定しているなら、まずは二等操縦士で十分
また、最初に二等を取得してから、将来的に一等へステップアップするルートも一般的です。費用や時間の観点からも段階的な取得は有効です。
ドローン国家資格の取得ステップ
ドローンの国家資格を取得するには、一定のプロセスに従う必要があります。単に試験を受けるだけではなく、国が認定した「登録講習機関」での講習や修了審査を経ることが前提となります。以下では、国家資格を取得するための一般的なステップを解説します。
登録講習機関での講習と修了審査
国家資格取得の第一歩は、国土交通省に登録された「登録講習機関(RTC)」で講習を受けることです。ここでは、以下の内容を体系的に学びます:
- 無人航空機の基本構造と操作理論
- 航空法・電波法などの関連法規
- 実際の操縦技術(シミュレーターおよび実機)
- 安全対策・リスクアセスメントの基礎
講習の最後には「修了審査」があり、これに合格することで国家試験のうち「実地試験」が免除される特典があります。つまり、登録講習機関での講習+審査は実技試験の代替として認められるのです(学科試験は別途受験が必要)。
学科試験と身体検査の流れ
登録講習機関で修了審査に合格した後は、指定試験機関での学科試験と身体検査を受ける必要があります。試験の実施主体は「一般財団法人 日本海事協会(JMC)」です。
- 学科試験はCBT方式(パソコンでの多肢選択式)で実施され、航空法、無人航空機の構造、運航管理などが出題されます。
- 身体検査では、視力、色覚、聴力、運動機能などがチェックされ、操縦に支障がないかを確認します。
学科試験の合格および身体検査の通過によって、国家資格の最終申請へと進むことができます。
免許の申請手続きと登録方法
すべての試験に合格した後は、国土交通省に対して無人航空機操縦士の免許申請を行います。具体的には以下のステップで進行します:
- 指定フォームでの申請(電子申請が主流)
- 登録免許税の納付(1,800円〜)
- 本人確認書類や証明書類の提出
- 登録完了後、「無人航空機操縦士技能証明書(カード)」が発行される
この証明書は、今後の飛行時に必要となるほか、飛行申請の免除や業務発注先への提示資料としても使用されます。
国家資格を取るための受験資格と条件
ドローンの国家資格(無人航空機操縦士)を取得するには、誰でもすぐに受験できるわけではありません。法律で定められた身体条件や年齢要件、技能・経験の有無など、いくつかの受験条件があります。ここでは、国家資格の取得を目指す際に確認すべきポイントを整理して解説します。
年齢や視力などの身体条件
国家資格を取得するためには、以下のような身体的条件を満たしている必要があります。
- 年齢制限:16歳以上(※一等・二等ともに)
- 視力:両目で0.7以上、かつ片目で0.3以上。メガネやコンタクトレンズの矯正視力も可。
- 色覚:赤・青・黄の区別がつくこと(色弱は個別対応)
- 聴力:通常会話が聞き取れるレベル(補聴器使用可)
- 運動能力:手足の自由な動作が可能であること
なお、身体条件を満たさない場合でも、特例措置(条件付き許可)を受けられるケースもあるため、該当者は事前に申告・相談することが重要です。
必要な経験・技能はある?
国家資格の取得に際して、飛行経験が必須というわけではありません。まったくの未経験者でも、登録講習機関で講習を受けながら操縦技術を習得し、修了審査に合格すれば資格取得が可能です。
ただし、独学で学科試験だけを目指す「経験者ルート」の場合は、一定の実技スキルがあることが前提です。そのため、初学者や経験が浅い方は登録講習機関での受講を強くおすすめします。
学歴やドローン歴の要件はある?
国家資格には、特別な学歴の制限は一切ありません。中卒・高卒・大卒など、どの学歴でも受験可能です。
また、ドローンの操縦歴や民間資格の有無も、国家資格の受験資格には直接影響しません。とはいえ、民間資格を保有している場合は、登録講習機関によっては講習の一部が免除される場合もあるため、事前に照会しておくとよいでしょう。
講習の内容とスケジュール
ドローン国家資格の取得には、国土交通省に登録された講習機関での受講が基本となります。特に未経験者や初心者の場合、講習は実地試験の免除にもつながる重要なプロセスです。ここでは、講習の具体的な内容とスケジュールの目安を詳しく解説します。
学科講習で学ぶ内容とは
学科講習では、ドローンの安全運用に必要な知識を体系的に学びます。主な内容は以下のとおりです:
- 航空法:無人航空機に関する法規制の理解(飛行禁止区域、飛行申請、飛行ルールなど)
- 電波法・道路交通法など:関連する法律の基礎
- 無人航空機の構造・機能:機体の構造、制御方法、通信システムの仕組み
- 気象の基礎知識:風速・風向、天気図の読み方、飛行への影響
- リスク管理と安全対策:事故の事例、リスクアセスメント、安全確認手順など
学科講習は、筆記試験(学科試験)への対策としても機能しており、知識ゼロの状態からでも理解できるようにカリキュラムが構成されています。
実地講習とシミュレーター訓練
実地講習では、実機またはシミュレーターを使用して操縦技術を学びます。主な訓練項目は以下のとおりです:
- 離陸・着陸操作
- GPSおよびATTIモードでの飛行操作
- 緊急時の対応(フェイルセーフ)
- 想定シナリオに基づく業務飛行の訓練
機関によっては、シミュレーターを併用しながら効率的に学ぶスタイルも多く、実際の飛行現場を意識した実践的なトレーニングが行われます。
講習時間と日数の目安
講習時間や日数は、資格の種類(1等または2等)や経験者・未経験者によって異なります。
| 資格種別 | 経験区分 | 講習時間(学科+実地) | 受講日数の目安 |
|---|---|---|---|
| 二等操縦士 | 初学者 | 約10〜15時間(2〜3日) | 約2〜3日 |
| 二等操縦士 | 経験者 | 約5〜7時間(1〜2日) | 約1〜2日 |
| 一等操縦士 | 初学者 | 約20〜25時間(4〜5日) | 約4〜5日 |
| 一等操縦士 | 経験者 | 約10〜15時間(2〜3日) | 約2〜3日 |
なお、オンラインでの事前学習や、短期集中講座などを活用することで、受講スケジュールを柔軟に調整できる場合もあります。
国家試験の概要と難易度
ドローンの国家資格を取得するためには、国が指定する試験機関で行われる「学科試験」と「身体検査」に合格しなければなりません。さらに、講習を受けない「経験者ルート」の場合には「実地試験」も課されます。このセクションでは、それぞれの試験の概要と難易度、合格に向けた対策のポイントを解説します。
学科試験の出題範囲と形式
学科試験は、CBT(Computer Based Testing)方式で実施され、パソコンを使って会場で受験します。試験の内容は以下の5科目です:
- 無人航空機のシステム・構造
- 運航に関する知識(気象・空域など)
- 航空法や電波法などの関連法規
- 安全な飛行に関する知識
- 人の心理・適性、リスクマネジメントなど
問題数は概ね40〜50問程度で、合格基準は全体の70%以上正答とされています。問題は四肢択一形式で出題され、事前に模擬試験などで対策をしておくことで合格の可能性が高まります。
実技試験の評価ポイント
講習を受けずに直接受験する「経験者ルート」では、実技試験も課されます。試験内容は以下のような操縦スキルを確認するものです:
- 安定したホバリング・離着陸操作
- 視線を外さずに目視での正確な飛行操作
- GPSモード、ATTIモード両方での運用
- 緊急時のフェイルセーフ操作
- 指示に応じた即時の対応能力
試験官が操縦技術だけでなく、安全意識、リスク判断力、冷静な対応力なども含めて総合的に評価します。なお、登録講習機関の修了審査に合格している場合は実技試験が免除されます。
合格率と対策方法
2024年度の平均合格率は以下のとおりです(公式発表に基づく):
- 二等操縦士 学科試験のみ:約75〜85%
- 一等操縦士 学科試験のみ:約65〜75%
- 実地試験(経験者ルート):一等で約50%、二等で約60〜70%
特に一等操縦士は試験の難易度が高く、事前の講習やシミュレーター訓練が合否を左右します。合格のためには、市販の対策テキストや過去問演習、講習機関の模擬試験を活用することが効果的です。
資格取得にかかる費用と期間
ドローン国家資格の取得には、講習費用・試験料・免許交付手数料など、さまざまなコストがかかります。また、資格取得までの期間も受講内容や個人のスケジュールによって異なります。ここでは、一般的な費用の目安と取得までにかかる時間を解説します。
講習費用の相場
講習費用は、登録講習機関や資格の種類、一等・二等、経験者・未経験者などによって大きく異なります。以下は代表的な費用の目安です。
| 資格区分 | 経験区分 | 講習費用の相場(税込) |
|---|---|---|
| 二等操縦士 | 初学者 | 約20〜30万円 |
| 二等操縦士 | 経験者 | 約10〜15万円 |
| 一等操縦士 | 初学者 | 約30〜50万円 |
| 一等操縦士 | 経験者 | 約15〜30万円 |
費用には学科・実地講習、修了審査、テキスト代、シミュレーター利用料などが含まれる場合が多いです。民間資格を持っている人は、受講時間の短縮や割引が適用されることもあります。
試験・登録・免許交付費用
講習以外にも以下の費用が発生します:
- 学科試験受験料:6,800円(税込)
- 身体検査料:3,000円〜5,000円(医療機関により異なる)
- 免許申請料(登録免許税):1,800円
- 証明書発行手数料:1,000円前後(講習機関による)
合計で1万円〜1万5千円程度が追加で必要となると考えておくとよいでしょう。
取得までの期間はどれくらい?
取得までの期間は、講習スケジュールや個人の学習進度によって異なりますが、以下が一般的な目安です。
- 二等操縦士(初学者):2週間〜1ヶ月程度
- 二等操縦士(経験者):最短1〜2日(講習+修了審査)
- 一等操縦士(初学者):1ヶ月〜1.5ヶ月程度
- 一等操縦士(経験者):2週間〜1ヶ月程度
早ければ、経験者であれば10日以内に取得することも可能です。ただし、試験予約の空き状況や講習日程、申請処理にかかる行政手続きの期間も考慮する必要があります。
登録講習機関の選び方と比較ポイント
ドローンの国家資格を取得するには、国土交通省が認定した「登録講習機関(RTC)」での受講が必要です。しかし、全国には多数の講習機関があり、内容・費用・サポート体制も異なります。このセクションでは、自分に合った講習機関を選ぶための判断ポイントを解説します。
国家資格に対応した教習所の選び方
まず大前提として、選ぶべきは国土交通省の登録講習機関(RTC)であることです。非登録の民間スクールでは、国家資格に必要な修了審査や実地免除が受けられません。
登録講習機関は全国に多数ありますが、以下のような観点で比較すると、自分に合った教習所が見つかりやすくなります:
- 一等・二等のどちらに対応しているか
- 初学者向けか、経験者向けか
- 学科・実地の講習が一貫して受けられるか
- 修了審査の合格実績やサポート体制
公式サイトに「国家資格対応」と明記されているかを必ず確認しましょう。
地域・料金・サポート体制の比較
講習機関の選定においては、地理的な通いやすさや料金体系も重要です。
- 立地:自宅や職場から近い、公共交通機関で通える場所か
- 料金:講習費用の内訳や、テキスト・修了審査料が含まれているか
- サポート:試験対策の教材提供、学科試験予約の補助、再受講のフォロー体制など
また、平日夜や週末に開講しているコース、短期集中コースを選べば、忙しい社会人でも通いやすくなります。
オンライン講習や短期集中コースはある?
最近では、学科講習をオンラインで受講できる講習機関も増えています。Zoomや独自のeラーニングシステムを活用し、効率的に学習できるのが魅力です。
また、以下のような特化型コースも存在します:
- 2日間の短期集中型コース
- 企業向けの団体講習・出張講習
- 女性・高齢者向けの専用プラン
- 英語対応や外国人向け講習
自分のライフスタイルや目的に合った講習スタイルを選べば、より無理なく国家資格の取得を目指せます。
国家資格を取得するメリットと活用方法
ドローンの国家資格を取得することで、単に法的な飛行が可能になるだけでなく、業務の幅が広がったり、就職・転職で有利になったりと多くのメリットがあります。ここでは、資格取得の具体的な利点と、活用できる主なシーンを紹介します。
飛行の幅が広がるシチュエーション
国家資格を取得すると、航空法で原則禁止されている飛行の一部が、事前承認なしで可能になるケースがあります。特に以下のような高度な飛行ができるようになるのが大きな特徴です。
- レベル4飛行(一等操縦士):補助者なしでの目視外飛行が可能に
- 夜間飛行、人口密集地での飛行
- 高層建築の近接飛行や施設点検での接近飛行
- 山間部や河川などでの長距離運航
これにより、業務効率の向上はもちろん、フットワークの軽い柔軟な対応が可能になります。
法令遵守とリスク低減につながる
国家資格を取得することで、法規制をしっかり理解したうえでの運航が可能となり、飛行時の事故リスクや法令違反のリスクを大幅に軽減できます。
また、講習ではリスクアセスメントや飛行計画の立て方、安全確認手順なども学ぶため、事故防止に対する意識が格段に向上します。
企業や自治体がドローン操縦者を選ぶ際、国家資格の有無が「信頼性の指標」として見られる傾向が強まっており、法令遵守を重視する現場では必須に近い資格となっています。
業務や副業での活用事例
国家資格を活かした実務は多岐にわたります。以下は代表的な業務例です:
- 建設・インフラ点検(橋梁、トンネル、ダム、送電線など)
- 測量・地図作成(国土交通省、自治体などの公共事業)
- 農業分野(農薬散布、作物管理)
- 物流・配達(レベル4飛行による宅配)
- 警備・監視業務(大型イベント、山林火災監視など)
- 空撮(映像制作、報道、広告など)
副業として個人で開業する場合も、国家資格があることで法人案件の受託や業務委託契約がしやすくなるなど、信頼性の面で大きなアドバンテージになります。
よくある質問(FAQ)
ドローンの国家資格については、制度が新しいこともあり多くの疑問や誤解が存在します。ここでは、特に多く寄せられる質問を厳選して分かりやすく解説します。
ドローンの国家資格を取るにはいくらかかりますか?
講習費用、試験料、申請手数料などを含めると、二等操縦士でおおよそ20〜35万円前後、一等操縦士で30〜50万円程度が相場です。講習機関や経験者/未経験者によっても異なりますが、全体で見れば1回の自動車教習所通いと同等か、やや安い程度の費用感です。
ドローン国家資格の取得に必要な期間は?
未経験者の場合でも、最短で2週間〜1ヶ月程度で取得可能です。講習が集中して行われる短期コースを利用すれば、もっと短期間での取得も可能です。経験者であれば数日で修了できるケースもあります。
どの資格が仕事に有利ですか?
業務内容によりますが、レベル4飛行や都市部での飛行を前提とする仕事には一等操縦士が求められる場合があります。一般的な点検・測量・空撮などでは二等操縦士で十分とされることが多いです。将来性を見据えて一等の取得を目指すのも有効です。
ドローン免許は将来なくなるって本当?
いいえ。2025年時点で**「ドローン免許がなくなる」という事実はありません**。むしろ、ドローンの国家資格制度は年々整備が進んでおり、将来的にはより多くの飛行に資格保有が求められる方向に進んでいます。制度変更の噂には注意が必要です。
初心者でも国家資格を取ることはできますか?
もちろん可能です。国家資格の制度は初心者の取得を前提としており、講習カリキュラムもゼロから学べるように設計されています。特に登録講習機関の講習+修了審査ルートを選べば、実地試験も免除され、初学者でも安心して挑戦できます。
独学での取得は可能ですか?
理論上は可能です。学科試験と実地試験を直接受験する「経験者ルート」では、講習を受けずに国家資格を取得することができます。ただし、実技試験の難易度が高いため、独学での合格はかなりの飛行経験と事前練習が必要です。初心者には講習ルートを強く推奨します。
すでに民間資格を持っている場合の優遇措置はありますか?
あります。講習機関によっては、JUIDAやDPAなどの民間資格保有者に対して、講習時間の短縮や受講料の割引などの優遇措置を設けている場合があります。また、民間資格で学んだ内容は国家資格取得時の学習にも役立ちます。